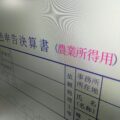よく聞かれる質問です。
社長が1年を振り返り来年を思いたい季節と、
顧問税理士が希望する時期が重なる月がいいですよ。
一般的に、決算月に良いと言われる月
まず、一般的に言われていることをまとめてみます。
① 税理士が忙しくない月
日本の会社は3月の決算が多いです。

本社や官公庁、社員の採用時期に合わせていたりする場合が多いです。
個人の確定申告は12月締めの3月申告なので、
税理士の忙しい時期に重なるのは、12月、1月、2月、3月決算となります。
税理士事務所によりますが、一般的には忙しければヒューマンエラーの可能性は上がり、
対応に割く時間も相対的に少なくなる事務所もあると考えられます。
とはいえ、確定申告をやらない税理士もいるので、あくまで一般的な話です。
② 最初の1年が12ヶ月ある月
例えば、9月に法人設立するなら8月を決算月にするという意味です。
1年目から売上が1000万円を超える見込みである場合に、
消費税が免税となる最初の2年をなるべく長くすれば、
消費税の節税になるという理由です。
たしかにそうですが、最初の1年の数カ月分だけに関係する話で、
3年目以降は関係ありません。
1、2年目から消費税がかかる例外もあるので、税理士にも相談しましょう。
消費税が免税なら関係ありません。
③ 売上高が多くない月
決算月の手前で、会社はその年の決算予測をして、
決算賞与や節税対策などを検討します。
ところが、決算月の売上が大きいと、
売上が変動した場合に対策が間に合いません。
だから、期首に売上が大きな時期、期末は売上の少ない時期が
良いと一般的には言われています。
季節性がある業種なら、ある程度の合理性はあると言えます。
④ 棚卸が少ない月
棚卸が多いと、棚卸が大変だから、という理由です。
これも業種によるでしょうか。
棚卸がしやすい月という意味だと思います。
毎月しているなら関係ありません。
⑤ 現預金の残高が多い月
納税資金に余裕を持つためという理由です。
キャッシュの流出を伴う節税もしやすくなると言われます。
そうかもしれませんが、法人の設立時に
そこまで具体的に計画できればよいですが…。
一般的には、上記のような理由を総合的に考慮して決めましょう、
という話が多いです。
わたしのすすめる決算月の決め方
わたしは、決算月は社長が好きな月で良いと思います。
税理士とゆっくり打ち合わせができる月ならば、なお良いです。
好きな月、というのは、具体的には以下です。
決算が近づくと、
自分の会社のこの1年間を振り返って、
これから先の1年のことを考えます。
いつもやっているかもしれませんが、
特に年度末は、利益と税金を確定させて、
来年再来年の計画に合わせて年度末までに届け出をしたり、
決算をしながら、次の1年間の役員報酬の金額を決めたりするわけです。
社長が、そういった振り返りや見通しを立てたいと思う季節が、
社長の「好きな月」ではないでしょうか。
本業がひまな時期に考えたいという社長も、
忙しい時期の直前(あるいは直後)に考えたいという社長もいると思います。
決算の作業や打ち合わせに取られる時間も考慮しつつ、
その気持を最優先しましょう。
一般的な理由は、参考程度で良いと思いますよ。
それから、顧問税理士に、「何月が良いですか?」と聞いてみることをおすすめします。
一般的には12月から3月が忙しいと言われていますが、
あなたの会社の顧問税理士は、3月が空いていて、たまたま9月が混んでいるかもしれません。
率直に聞けば、
「何月でも良いですが、○月は比較的空いていて、丁寧なご対応ができると思います」とか、
「○月は回答も遅くなってしまうので、できれば避けてください」とか、教えてくれると思います。
わざわざ税理士が忙しそうな月にして、
お金を払っているのに気を使うのもやりにくいですよね。
法人の決算は税理士との二人三脚ですから、
税理士に気を遣うというより、自社が気持ちよくベストなサービスを受けるためにおすすめします。
なんとなく3月というのはおすすめしませんが、
取引先や事業の都合で3月にしかできない場合は仕方がありません。
そういった場合には、決算作業がスムーズに進むことを特に念頭に、
期中の処理を整理していきましょう。
決算日は自由ですが、末日がおすすめ。
決算日は、絶対に末日でなければいけないわけではありません。
期首を設立日や記念日にしたければ、できないことはありません。
でも、おすすめしません。
月の途中が期末日の場合には、余分な作業が発生します。
よほどの事情がなければ、決算日は月の末日をおすすめします。
なお、決算月は途中で変更もできます。
手続きとお金は多少かかりますが、
変更したければ、変更したほうが良いです。
最初に決めたら二度と変更できないわけではありません。